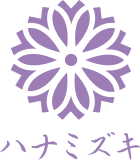かつて日本では、「家」と「墓」は一体でした。
お墓は代々受け継ぎ、家族や地域社会の絆を象徴する存在。盆や彼岸には親族が集まり、墓参りを通して家族の歴史を確かめ合ってきました。
しかし今、その伝統が大きく揺らいでいます。
それが、近年急増している「墓じまい」という現象です。
墓じまいが増える背景
背景には、日本社会の急激な変化があります。
- 人口移動の歴史的転換
高度経済成長期、地方から都市へ多くの人が移り住みました。都会で生活基盤を築いた子や孫は、ふるさとの墓から離れた暮らしを余儀なくされます。 - 少子高齢化と後継者不在
子どもの数が減り、未婚化・非同居化が進む中で「お墓を守る人」がいなくなる。 - 経済的負担
墓の維持には管理費や法要費がかかり、長期的に続けることが難しい家庭も増えています。 - 価値観の多様化
樹木葬や納骨堂、海洋散骨など、多様な供養方法が選択肢となり、必ずしも「石のお墓」にこだわらなくなっています。
墓じまいの現実と課題
墓じまいは単なる撤去作業ではなく、自治体への改葬許可申請や閉眼供養、遺骨の移動など、宗教的・法的な手続きが伴います。
また、親族の中には「先祖の墓を壊すこと」に抵抗感を持つ人も少なくありません。感情的な対立や、意見のすれ違いがトラブルに発展することもあります。
さらに、後継者がいない墓が放置されると「無縁墓」となり、自治体が改葬や撤去を行うケースも増えています。
厚生労働省によると、自治体による無縁墓改葬件数は年間3,000件を超え、今後も増加が予想されます。
コロナ禍がもたらした加速
2020年以降の新型コロナウイルス感染拡大は、高齢者の意識を大きく変えました。
「自分がもし急に亡くなったら、お墓はどうなるのか」という不安が現実味を帯び、先延ばしにしてきた墓じまいを実行する動きが急増しました。
実際、改葬件数は2000年度の約6万6千件から、2022年度には15万件を超えています。
これからの供養の形
墓じまい問題は、単に「墓を減らす」という話ではありません。
むしろ、どうすれば将来にわたって故人を尊び、安心して供養を続けられるかという問いかけです。
地方の墓を都市部に移す、永代供養墓に改葬する、樹木葬で自然に還す――選択肢は広がりました。
大切なのは、故人の意志や家族の想いを尊重しつつ、現実的に維持可能な方法を見つけることです。
まとめ
墓じまい問題は、日本社会の高齢化や人口構造の変化を映し出す鏡のような存在です。
これは個人や家族だけの問題ではなく、地域や社会全体で向き合うべき課題でもあります。
お墓をどうするか――。
それは、過去と未来をどうつなぐかを考えることでもあります。
後回しにせず、元気なうちに、家族でじっくり話し合うことが何より大切です。
改葬は、一度きりの大切な決断です。
距離のあるふるさとの墓や、将来継ぐ人のいないお墓も、今なら安心して移す方法があります。
ハナミズキでは、法的手続きからご遺骨の移動、永代供養まで一貫してサポート。
「いつかやろう」と思っていたことを、今こそ一緒に形にしませんか。
まずは無料相談から、お気軽にご連絡ください。